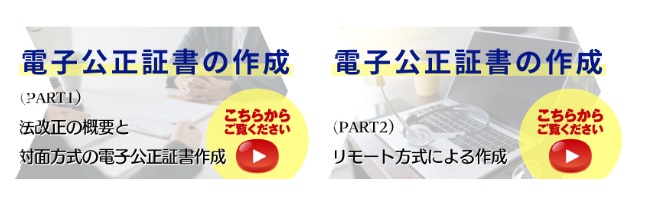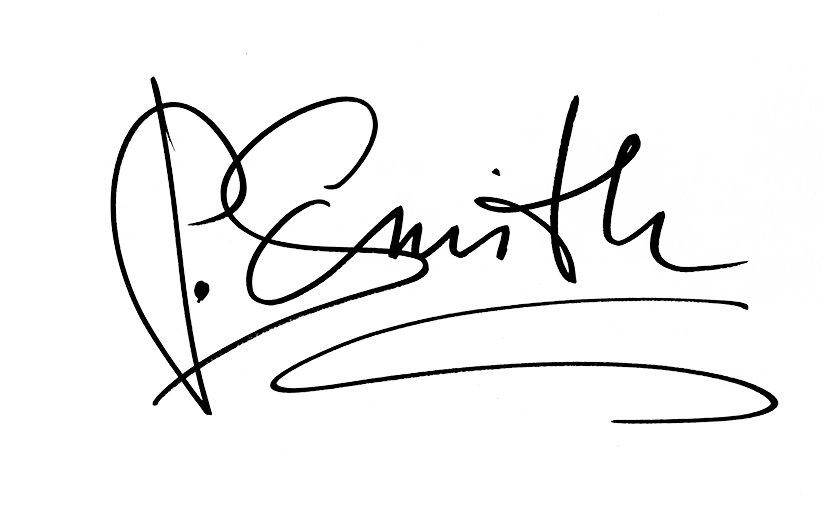Tokyo Musashino Notary Office
武蔵野公証役場
公正証書遺言書、任意後見契約、保証意思宣明公正証書などの作成、定款認証は当役場へ(相談は無料です)
お知らせ/What's New
令和8年4月から民法の一部改正法が施行されます~離婚を検討されている方は、時期や内容にご注意ください
令和6年5月に成立した民法の一部改正法(令和6年法律第33号) が令和8年4月1日から施行されます。
主な内容として
① 親の責務等に関する規律を新設
② 親権・監護等に関する規律の見直し
③ 養育費の履行確保に向けた見直し
④ 安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
⑤ その他(財産分与・養子縁組に関するルール等)の見直し
がありますが、
養育費等に関する経過措置としては
①養育費債権の先取特権 施行日前に養育費等の取決めがされた場合には、 施行日以後に生じた各期の定期金に適用される
② 法定養育費 施行日前に離婚した場合等には適用されない
③ 親権者変更 施行日前にされた親権者変更の申立てについて、 家庭裁判所が判断をする時期が施行日後となる場合には、 単独親権から共同親権への変更が可能
離婚を検討されている未成年の子どもがいるご夫婦には、離婚の時期や合意する内容に影響がありますので、ご注意をお願いします。
詳しくは、法務省のサイトをご覧ください。https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00357.html
電子定款認証に係る申請方法が拡大されました
1)電子定款の認証対象となる電子文書は、PDF形式で電子署名されたものからPDFファイルにXML形式で電子署名されたものも可能
2)発起人の委任状に複数の発起人がXML形式で電子署名することも可能
3)1申請1定款申請から同一申請で定款に加えて複数の電子委任状を添付して申請が可能
となり、使い勝手が良くなりました。
詳しいことは、日本公証人連合会のサイトをご覧ください。
https://www.koshonin.gr.jp/news/nikkoren/expansion_method.html
養育費援助のある自治体の情報がアップデートされました
東京会が公開している都内で養育費確保支援事業を行っている自治体(区、市)の情報がアップデートされました。
詳しくは東京会のサイトをご覧ください。https://www.tokyokoshonin-kyokai.jp/yoikuhi/
日本公証人連合会(日公連)では、法務省の協力の下で、起業支援の観点から、小規模でシンプルな形態の株式会社(発起人3人以内、取締役会非設置など)
をスピーディーに設立したいという起業者のニーズに応えるため、「定款作成支援ツール」を作成しました。
どなたでも自由に使えるツールとなっています。
また、東京と福岡では、令和6年1月10日から、この定款作成支援ツールを使用して定款認証を受けようとする場合には、原則として48時間以内に定款認証手続を完了させる特別処理を開始し、同年9月20日からは埼玉、千葉、神奈川、愛知の各県及び大阪府内にも、令和7年3月からは全国の公証役場に拡大されました。
詳しくは、下記の日公連のサイトをご覧いただき、ツールはダウンロードしてご利用ください。
なお、留意点や、48時間以内に完了するためには、一定の条件がありますので、注書きなどもよくご確認ください。
令和7年10月から公正証書の電子化(デジタル化)が始まります~情報提供①
既にお知らせしている通り、令和5年6月に民事執行手続、倒産手続、家事事件手続等の民事関係手続のデジタル化を図るための規定の整備等を行う改正法(民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和5年法律第53号))が成立したため、令和7年10月から開始されます。
公証関係で大きく変わるのは、公正証書がデジタル化(電子ファイル)されることですが、これまでと変わらない点も多くありますので、これから、これまでに分かっている情報を提供していきます(複数回にわたります)。
▪️電子化されない公正証書
保証意思宣明公正証書は、法律上電子化が除外されています。したがって、変更はありません(紙で公正証書が作成されます)。
▼変更されない点(嘱託人の必要になる書類や手続きに大きな変更はありません)
遺言や、離婚や養育費の支払に関する契約など依頼者の方の関心が高い公正証書の作成については、必要となる書類や手続きに大きな変更はありません。これまで通り、嘱託人の身分証明書は印鑑登録証明書(作成時に実印の持参が必要)やマイナンバーカード、免許証などの写真付公的証明書で構いません。作成時には、タッチペンを用いてサインをしてもらいますが、これは従前はペンで署名していただいたことと同じです。ただ「押印」は必要がなくなりますが、内容確認のうえで「適用」のキーを押すなどの作業があります。
原本は電子化され、依頼者には正本や謄本といった情報も電子化されたデータで提供されますが、依頼者の希望があれば、これまで通り「正本」「謄本」に相当する紙での交付も可能です(手数料は必要となりますが、これも変更はありません)。
送達等の手続きにも変更はなく、これまで通り紙(謄本)での手続きとなります。
公正証書の電子化(デジタル化)が始まります~情報提供②
今回の電子公正証書の電子化で可能となるのが、リモート(Web会議)での公正証書の作成です。
ただし、すべての場合にリモートが可能となるわけではありません。
現時点でわかっている点を説明します。※開始時点での仕様です。今後の利用状況によっては変更される場合があります。
リモート作成のための諸要件(条件)
1)必要な機材等
リモートで作成するためには、パソコン(Macも可)が必要であり、それにWebカメラ、マイク、イヤホン(スピーカー)などが備わっていることが必要となります。※スマホやタブレットでの利用はできません。
また、電子署名するためのタッチ入力が可能なディスプレイ、ペンタブレット、メールでやり取りするためのアドレスも必要です。
ソフトは、Microsoft Teams を利用します。※これも他のソフトでの利用はできません。
2)利用できるのは希望者だけ(申出が必要)
他の嘱託人から反対があると利用できません。
(注)通訳人や立会人の反対(異議)は関係ありません。
3)公証人がリモート利用を相当であると認めることが必要
公証人はリモート作成の必要性と許容性を勘案して、相当かどうか判断します。
公証人が相当と認めなければ、リモートでの作成はできません。
4)保証意思宣明公正証書はリモート作成から除外されています
従って、実際に利用されることになるのは、離婚の際の養育費の支払いなどの合意、賃貸借や金銭消費貸借(債務承認と弁済合意)などの契約、そして遺言書になるのではないでしょうか。
遺言書の作成はご高齢者が多いので、対面での作成や作成された遺言書を紙で受取りたいと希望する方が多いこと、上記の諸条件を満たす場合が少ないこと、特に周囲の方の影響を受けないで作成手順を行うことは、パソコン操作に慣れていないと難しいかもしれません。
もちろん、ご高齢者であっても(高齢者に限りませんが)パソコン操作等に慣れていてリモート作成を希望し、かつ公証人が相当と認めれば、利用することが可能となります。
もし、ご希望があれば、遠慮なく担当公証人と事前に相談してください。
公正証書の電子化(デジタル化)が始まります~情報提供③
日本公証人連合会のウェブサイトでは、電子公正証書の運用開始に向けた動画を2本公開しています。
1本は法改正の概要と対面方式の電子公正証書の作成、もう1本はリモート方式による作成です。
前者は遺言書の作成、後者は離婚の際の公正証書の作成が例とされています。電子化が開始されたときの参考になると思われますので、関心のある方はご覧ください。https://www.koshonin.gr.jp/
当役場では、令和7年10月20日(月)から開始されました~情報提供④
法務大臣からの指定により各役場で公正証書の電子化が可能となりますが、当役場では令和7年10月20日(月)から始まりました。
全国では令和7年12月15日から始まっています。
タッチペンを用いた署名、作成時に押印が必要なくなるなど変更となる点があります。
特に、開始以降に作成を予定されている方、逆に開始より前では従前と同じ方式で作成するため(ペンでの署名や押印が必要)ご注意願います。※※上記の通り、保証意思宣明公正証書の作成に変更はありません(10月20日以降も押印が必要です)。
ご心配な方は、事前に当役場までお問い合わせください。

このコーナーでは、人気の街 吉祥寺や役場の内外でのでき事やニュースを取り上げたいと思います。
少し堅いと思われているこのサイトをご覧いただいた方に、肩の凝らないニュースや情報を提供し、当役場や公証業務について少しでも関心を持ち、理解を深めていただきたいと願っています。

もう直ぐ春ですね
先日の冬季オリンピックでは、若い日本選手の活躍が目立ちました。3月には野球のWBCも始まります。また日本中が盛り上がることでしょう。
公証役場では、春になっても大きく変わることはありませんが、昨秋から始まった公正証書の電子化も定着しつつあり、遺言書作成の方にはタッチペンでのサインをお願いしています。
幸い、これまで体の不自由な方を除いてサインができなかったという事例はありませんでした。
今後とも公正証書作成へのご理解とご協力をお願いいたします。